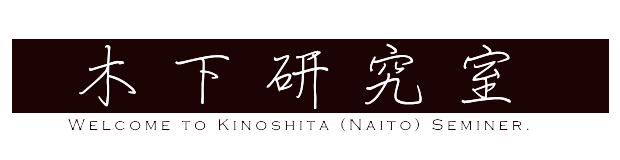目次
1. パーソナリティー研究
2. メディア研究
3. 抑うつにおける情報処理過程の研究
4. 食の心理学研究
パーソナリティ研究
a. 卒論と修論で、Cloninger et al. (1993) のTCI (Temperament and Character Inventory)
を取り上げました。学部4年生の時、パーソナリティのなかの、気質の側面に興味をもちました。Cloninger et al. によるTCIでは、気質が神経伝達物質を基盤にもつと仮定されていることを、論文を読んで知りました。その当時、気質と同様に抑うつにも関心があったので、TCIと抑うつの関連・因果関係を検討しました。「抑うつの病前性格」研究と考えていただければいいと思います。その分野では、まだ
TCI の特性を検討していなかったので、探索的に研究を行いました。その結果を、Journal of Clinical Psychology と性格心理学研究の論文にまとめました。
b. Eysenck (1967) による内向性-外向性 (E) 次元は、生物学的な基盤を持つことが想定されており、多くの心理生理学的研究が行われています。この研究では、事象関連電位のP300成分の関連を調べました。内向性‐外向性では、
注意資源の配分の仕方が異なるため、P300 の振幅の馴化パターンが相違するとされてきました。そこで、注意要因(あり/なし)を 加えて追試を行ったところ、注意あり群で外向性群のP300の振幅が馴化し、先行研究を支持する結果が得られました。この実験結果は日本心理学会にて発表し、性格心理学研究に論文が掲載されました。
メディア研究
インターネット等の各種メディアの教育効果や心理的な影響を検討しています。
a. インターネット使用が情報活用の実践力に及ぼす効果を検討しました。現在、学校現場にイはンターネットが盛んに導入されています。その教育効果を信頼性の高い研究手法により、明確することが必要であると考え、中学生を対象に、準実験を行い、インターネットを学校に導入することで、情報活用の実践力が伸びるかどうかを調べました。その成果は、日本心理学会にて結果を発表し、日本教育工学会論文誌に論文が掲載されました。
b. また、インターネット上の自助集団に関する研究紹介もしています。インターネットでは同じ問題や悩みを抱えた当事者やその家族が集まり、お互いに励ましあう自助集団のサイトが多くみられます。そこで、インターネット上の自助集団で、どのような会話が交わされているか、またその効果について、「インターネットと心理学」中の6章で研究レビューをしています。
c. 自助集団と関連していますが、インターネットを使ったサイコセラピーの効果についても先行研究のレビューを行っています。インターネット・セラピーというと、一般にはメールを使ったものという印象が強いようですが、実際にはテレビ会議やチャット、MUDなど、種々のインターネット・ツールが用いられています。治療者と直に接する従来のセラピーと同様に、そうしたバーチャル・セラピーが人の心を癒すのかどうか、レビュー研究にて検討しています。「メディアと人間の発達-テレビ、テレビゲーム、インターネット、そしてロボットの心理的影響‐」中の11章にて、その詳細を紹介しています。
d.最近はメディアとの付き合い方についても関心があります。例えば、現代の子どもたちは各種の新しいメディア(テレビゲーム・インターネット・携帯電話など)が身近にあります。これらのメディアは親世代が子どもの頃には存在しなかったため、子どもたちが新しいメディアとどのように付き合えばよいかわからず、とまどっている保護者は少なくありません。しかし、子どもたちへの影響の大きさを考えると早急な対応が必要です。怖いものに近づけないのではなく、子どもの発達にプラスに作用するようなメディアの使い方を探っていければと思っています。このような私見を「リスク社会におけるコミュニケーション」「児童心理学の進歩」の各章にまとめました。
抑うつにおける情報処理過程の研究
現在は、抑うつ的な人に特徴的な(非抑うつ的な人と異なる)情報処理について研究しています。Pacini et al. (1998) は、人の情報処理における2つの様式、経験的処理と合理的処理
(Epstein, 1994) により、抑うつ者の情報処理を説明しました。経験的処理とはヒューリスティックな性質を持ち、合理的処理は熟慮を要する論理的な性質、とされています。Pacini
et al. は抑うつ者が重要な状況で合理的処理を行えないと主張しました。彼女らはこの仮説を実験により検証しましたが、支持されませんでした。そこで、私は実験手続きを修正して再検討を行ったところ、抑うつ者は重要でない状況で経験的処理をせず(International
Congress of Psychologyにて発表)、重要な状況で合理的処理をしないことが示唆されました(Asian Association
of Social Psychologyにて発表)。
そこで、合理的処理と抑うつの因果関係を検討し、合理的処理をする個人は抑うつ悪化を防ぐことができるとの結果を得ました(日本心理学会にて発表)。また、合理的処理と抑うつの間には、ネガティブな認知という媒介要因が存在することも確かめています(日本性格心理学界にて発表)。
これまで得た結果は博士論文にまとめ、「抑うつからの回復」と題して刊行しました。今後は、情報処理へのどのような介入が、抑うつの軽減や回復を促進できるかなど明らかにしていきたいと思っています。
*抑うつを研究していますが、カウンセリングはできません。私はいわば細胞レベルで病気のメカニズムを調べている病理医のようなもので、各種治療法を施す臨床医ともいえるカウンセラーとは異なります。こころの中に悩みを抱えて辛いときは、学生相談室(1号館1階にあります)や高崎市の保健福祉事務所(業務案内:027-322-5101)を訪問してください。あなたの心が軽くなるように尽力してくれます。
また、以下のサイトも紹介しておきます(URLをブラウザにコピーしてご覧になってください)。
UTU-NET うつネット
http://www.utu-net.com/
うつ、不安、パニックに関するサイトです。読みやすく、体験談から医療情報まで充実しています。バーチャルでメンタルクリニックの来院体験もできるので、病院に行くのはちょっと・・・とためらう時には試してみましょう。
群馬県こころの健康センター
http://www.pref.gunma.jp/c/05/seishin/top.htm
各都道府県には精神保健福祉センターがあり、心の悩みを抱えている人に無料で対応してくれます。全国のセンターへリンクが張ってあります。
いのちの電話(リンク多い)
http://www.find-j.jp/
24時間相談を受け付けている「いのちの電話」ですが、今はメールでも対応しています。広く心の問題に関するサイトも紹介してあります。
食の心理学研究
近年の心理学では、実験室を飛び出して、暮らしの中に活きる研究をしようという動きが強まっています。その問題意識から行っているのが食研究です。
2005年には、農畜産業振興機構から研究助成を受け、「甘いもの」に関する研究を行いました。その結果、「甘いもの」の摂取量が不安の軽減につながると同時に、肥満などの
健康懸念を高め、その結果不安が増加するというプラスとマイナスの影響力があることを提案しました。
また、2012年の共同研究では、食行動は、単に栄養を摂取する生理的なものではなく、対人交流や感情コントロールを含めた心理的現象であることを考察しています。
今後は、近年の心理療法を語る上で欠かせない<マインドフルネス>をキーワードに、摂食行動の心理的介入を検討する予定です。