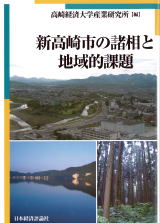
2012年3月発行
昭和51年度に研究所独自のテーマ設定と予算に基づく共同研究としてプロジェクト研究が開始された.研究成果を昭和54年に刊行,その後ほぼ毎年1冊のペースで刊行されている.こうした共同研究−著作活動を行っている大学研究所は全国的にみても稀であり,私達が最も誇りとする事業である. プロジェクト研究は,内容的には,高崎〜群馬を基軸的対象・念頭に置きつつ,歴史(経済史・思想史)・現代の2つの分野で様々な角度からなされてきたのであるが,従来,体系的・集中的に取り組まれていなかった分野が多く,多くの著書が多少とも開拓的意義を持ったと考えている.
| 新高崎市の諸相と地域的課題 | 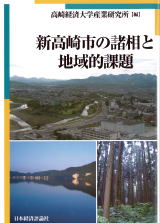 2012年3月発行 |
| 高崎経済大学産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 新高崎市前史 | 高階勇輔 西野寿章 |
| 第2章 新高崎市の地理的特色 | 西野寿章 |
| 第3章 高崎市の農業構造・農業振興政策・多様な経営展開 | 村山元展 |
| 第4章 新高崎市の森林資源 | 西野寿章 |
| 第5章 新高崎市の工業の特色と将来展望 | 河藤佳彦 |
| 第6章 新高崎市の商業 | 北條勇作 戸所 隆 加藤健太 |
| 第7章 新高崎市の観光 | 西野寿章 戸所 隆 |
| 第8章 高崎市の路線バスの変遷とそこに内在した諸問題の考察 | 大島登志彦 |
| 第9章 新高崎市の行財政 | 西野寿章 |
| 第10章 高崎市議会の制度的変遷と課題 | 増田正 |
| 第11章 データでみる新高崎市の金融 | 今野昌信 |
| 第12章 新高崎市と社会福祉 -高齢者福祉を中心に- | 熊澤利和 |
| 第13章 新高崎市の教育 | 吉原美那子 櫻井常矢 |
| 第14章 新高崎市の文化振興 | 友岡邦之 |
| 第15章 新高崎市の地域的課題 | 西野寿章 |
| 前高崎市長 松浦幸雄氏に聞く -高崎市の変貌と課題- | 高階勇輔 |
| ソーシャル・キャピタル論の探究 |  2011年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 序章 ソーシャル・キャピタル論とは何か | 今井雅和 |
| 第1章 地域安全マップづくりを通した地域コミュニティの醸成 | 伊藤亜都子 |
| 第2章 大学教員による市民活動ネットワークの形成 | 久宗周二 |
| 第3章 地域活性化とソーシャル・キャピタル | 坪井明彦 |
| 第4章 ソーシャル・キャピタルの形成要因分析 | 阿部圭司 |
| 第5章 事業創造とイスラーム思想 | 今井雅和 |
| 第6章 「豊かさ」をもたらす社会的企業と資金調達 | 前田拓生 |
| 第7章 ソーシャル・キャピタル概念と情報開示 | 水口 剛 |
| 第8章 社会ネットワーク中心性と組織構造集権化との接点を探る | 藤本 哲 |
| 第9章 多国籍企業のマネジメントとソーシャル・キャピタル | 清水さゆり |
| 第10章 ホスピタリティとソーシャル・キャピタル | 徳江順一郎 |
| 第11章 ソーシャル・キャピタルと経済成長 | 中野正裕 |
| 地方公立大学の未来 |  2010年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 序章 地域との連携により地域の未来を創る地方公立大学 | 戸所 隆 |
| 第1章 データで見る地方公立大学の諸相 | 石川弘道 |
| 第2章 変わりゆく大学教育と大学の未来 | 高松正毅 |
| 第3章 研究教育活動と地域—ゼミナール活動を事例として | 西野寿章 |
| 第4章 公立大学における職員の能力開発(SD) | 大石 恵 |
| 第5章 教員養成課程における「子どもの抑うつ防止教育」と地域の健康づくり | 内藤まゆみ |
| 第6章 地方公立大学のスポーツマネジメント—地域性を活かした大学づくりをめざして | 高橋伸次 |
| 第7章 地方公立大学にとっての卒業生の重要性−ゼミを媒介としたネットワークの形成 | 矢野修一 |
| 第8章 OECDによる日本の大学評価と地方公立大学の未来 | 戸所 隆 |
| 終章 地方公立大学の役割と未来 | 戸所 隆 |
| 群馬産業遺産の諸相 |  2009年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| はじめに | 大島登志彦 |
| 第1章 産業考古学における産業遺産研究 | |
| I わが国における産業考古学の研究系譜と問題点 | 青木栄一 |
| II 鉄道の発達からみた群馬の産業史とその遺産の点描 | 大島登志彦 |
| 第2章 群馬県における鉱工業の展開とその遺産 | |
| I 日本の近代化における中小坂鉄山の意義と遺産の概要 | 原田 喬 |
| II 吾妻郡の鉱山と閉山後の現況 | 下谷昌幸 |
| III 高崎亜炭鉱業の歴史と産業遺産 | 高階勇輔 |
| IV 群馬県の重化学工業化と浅野財閥・理研コンツェルン−「産業遺産」化研究序論 | 小池重喜 |
| 第3章 富岡製糸場と絹産業遺産群の世界遺産化とその課題 | |
| I 富岡製糸場の保存とその活性化に向けた街づくりにみる諸問題 | 桑島 裕 |
| II 市民の支援と産業遺産の関わり | 山﨑益吉 |
| III 養蚕・製糸業を支えた風穴の分布とその意義 | 原田 喬 |
| IV 碓氷峠鉄道施設の保存と活用−歩みと世界遺産化への課題− | 西野寿章 |
| 第4章 群馬県の伝統産業と生活文化 | |
| I 群馬県方言における<養蚕空間>を表す語彙 | 新井小枝子 |
| II 鐘紡の労務管理と新町紡績所の終末期の操業形態 | 久宗周二 |
| III 暮らしを支える民俗遺産−「石」に生かされた群馬の「地域」から− | 千葉 貢 |
| IV 下仁田森林鉄道の形成と住民の利用形態 | 中牧 崇 |
| 第5章 地域産業の展開とその歴史的評価 | |
| I 近代化産業遺産保存の将来と活性化の課題−社会経済学からの接近− | 武井 昭 |
| II 群馬県における蒟蒻精粉業の史的展開 | 岸田孝弥 |
| おわりに | 大島登志彦 |
| サステイナブル社会とアメニティ |  2008年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 序章 持続社会の発展 | 加藤一郎 |
| 第I部 サステイナブル社会の課題 | |
| 第1章 持続型社会への金融アプローチ | 山田博文 |
| 第2章 特続可能な社会を支える投資行動−「責任ある投資」概念の普及と実践の課題 | 水口 剛 |
| 第3章 戦前における電気利用組合の展開とその地域的役割 | 西野寿章 |
| 第4章 持続可能性と連帯経済−プロジェクト・スモール・エックスヘのまなざし | 矢野修一 |
| 第II部 環境・アメニティの経済分析 | |
| 第5章 コモンズの悲劇と非線形経済動学 | 柳瀬明彦 |
| 第6章 地域環境政策における経済的手段の導入と公衆の参加 | 浜本光紹 |
| 第7章 エコツーリズムの経済分析−コモンプールアプローチ | 伊佐良次・薮田雅弘 |
| 第III部 環境・アメニティ政策の評価 | |
| 第8章 低炭素社会に向けた地方自治体における取り組み−戦略的政策形成の課題と展望 | 林 宰司 |
| 第9章 GM産品へのEUラベリング政策の評価をめぐって−貿易摩擦から"新しい環境アカウンタビリティ"へ | 山川俊和 |
| 第10章 尾瀬におけるガイドツアーに対する紅葉期入山者の選好分析 | 柘植隆宏・庄子 康・荒井裕二 |
| 第11章 群馬の森の環境評価−仮想評価法およびトラベルコスト法による実証 | 柳瀬明彦・小安秀平・中条 護・堀田知宏・水野玲子 |
| 新地場産業と産業環境の現在 |  2007年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 新地場産業と産業環境の現在 | 武井 昭 |
| 第2章 危機に喘ぐ中小企業の現状・課題・展望 | 吉田敬一 |
| 第3章 地域産業の創出発展と基本理念-コミュニティビジネスを中心にして | 長谷川秀男 |
| 第4章 産業環境の変容と環境産業 | 林 宰司 |
| 第5章 山間地域農業振興への地域政策からの接近-群馬県西毛山村を事例として | 西野寿章 |
| 第6章 地域産業への技術支援-変革期の地方公施設の役割 | 植松 豊 |
| 第7章 群馬の中小企業と組織開発 | 三谷徹男 |
| 第8章 産業場面におけるKAIZEN-ダイカスト工業を事例にして | 岸田孝弥・伊藤 匠 |
| 第9章 エコツアーのマーケティングリサーチ-環境保全と観光振興の両立を目指して | 柘植隆宏・庄子 康 |
| 第10章 地域金融の理念と現実 | 木元正司 |
| 第11章 地場産業の資金調達と株式公開 | 野崎 明 |
| 事業創造論の構築 |  2006年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 事業創造の新たな視点:ソーシャル・キャピタル,社会起業家,社会志向的企業と企業間連携 | 佐々木茂 |
| 第2章 市場経済システムの多様性とボランタリー活動 | 中野正裕 |
| 第3章 起業家のソーシャル・キャピタルとはなにか | 今井雅和 |
| 第4章 社会的責任投資とNPOからみた事業概念 | 水口 剛 |
| 第5章 ソーシャル・キャピタルが事業運営にもたらす影響度:アンケート調査と質的データを用いた分析 | 新井圭太 |
| 第6章 ベンチャー・ビジネスの競争戦略と産業集積の機能:産業集積におけるソーシャル・キャピタルの議論を踏まえて | 関根雅則 |
| 第7章 コーポレート・ベンチャーによる新規事業創造:母体企業の役割 | 飛田幸宏 |
| 第8章 起業家的マーケティングの概念枠組み:価値創造のためのネットワークの構築と活用 | 坪井明彦 |
| 第9章 国際化時代におけるベンチャー・ビジネスと地域金融 | 今野昌信 |
| 第10章 コミュニティ・ビジネスのためのファンディング・システム | 阿部圭司 |
| 第11章 非営利組織における業績評価問題 | 中村彰良 |
| 第12章 新規事業創造:セーラー万年筆の事例 | 清水さゆり |
| 循環共生社会と地域づくり |  2005年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 循環共生型地域社会づくりの課題−地域産業政策の視点から | 長谷川秀男 |
| 第2章 循環共生型国土構造・都市社会の構築 | 戸所 隆 |
| 第3章 「循環協働社会」と地域福祉−社会経済システムからの接近 | 武井 昭 |
| 第4章 農業・農村の活性化と循環・共生型システム | 吉田俊幸 |
| 第5章 中山間地域農業振興への政策的視点 | 西野寿章 |
| 第6章 農地保全をめぐる政策展開と課題−農業政策と都市計画 | 村山元展 |
| 第7章 表明選好法による環境政策の評価 | 柘植隆宏 |
| 第8章 自治体によるPETボトル回収 | 高橋美佐・加藤憲一 |
| 第9章 「ものづくり能力」とクラスターマネジメント | 黒川基裕 |
| 第10章 商業集積の形成と崩壊のモデル分析 | 吾郷貴紀 |
| 第11章 地域金融とリレーションシップ−持続可能な発展を視野に | 木本正司 |
| 第12章 情報循環による共生の場づくり−特別養護老人ホーム菱風園の試み | 池田俊憲 |
| 近代群馬の民衆思想−経世済民の系譜− |  2004年2月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 近代群馬の民衆思想−経世済民の系譜− | 山﨑 益吉 |
| 第2章 宮口二郎−捧げ尽くした生涯と思想 | 久保 千一 |
| 第3章 新井領一郎の思想と足跡−日本の「近代化」と「生糸直輸出」をめぐる諸思想の交錯のなかで− | 飯岡 秀夫 |
| 第4章 新井紀一における民衆と文学 | 大和田 茂 |
| 第5章 在野の啓蒙家・岡部栄信−「修己治人」「知行合一」の常民思想− | 千葉 貢 |
| 第6章 「生活の発見会」運動と家庭教育の復権−永杉喜輔の家庭教育論の意図するもの− | 野口 周一 |
| 第7章 高崎線建設に関わる地方の民衆意識−高崎線沿線の鉄道忌避伝承の検討− | 桑島 裕 |
| IPネットワーク社会と都市型産業 |  2003年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 見えない未来−IPネットワーク社会の正体 | 山本 喜則 |
| 第2章 「都市型産業」のダイナミズムと情報サービス | 武井 昭 |
| 第3章 情報化と地理的空間の関−都市システムの形成と情報化を中心に−係 | 津川 康雄 |
| 第4章 テレワークと都市型産業 | 松岡 温彦 |
| 第5章 地方都市中心市街地再生戦略と都市型産業−中心市街地再生と公共空間整備− | 山浦 瑛子 |
| 第6章 生活環境という視点からの都市型サービス産業の可能性 | 水野 統夫 |
| 第7章 地域金融における顧客満足 | 木元 正司 |
| 第8章 サービス化社会におけるマーケティング技法−顧客満足から顧客ロイヤルティの構築− | 坂尾 英幸 |
| 第9章 産業の創出とビジネス・インキュベーション | 中沢 洋一 |
| 第10章 「都市型産業」とe-ビジネス | 四宮 孝史・岸田考弥 |
| 第11章 都市が生んだeビジネススタイル−なぜSOHOは都市に集まるのか− | 眞崎 昭彦 |
| 都市型産業と地域零細サービス業 |  2003年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編、武井 昭・岸田考弥 著 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 「都市型から「都市型化」への転換と北関東 | |
| 第2章 「首都圏」における都市発展のダイナミズム群馬 | |
| 第3章 第1期「都市型産業」の発展と地域中小企業 | |
| 第4章 第2期「都市型産業」の発展と都市型工業 | |
| 第5章 LPガス販売事業のシステム化と産業再構築 | |
| 第6章 理容業のシステム化・サービス化と経営戦略 | |
| 第7章 サービス業としての柔道整復師業の経営者の意識と経営戦略 | |
| ベンチャー型社会の到来−起業家精神と創業環境− |  2002年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 起業家精神の昂揚と知識・顧客創造の経営 | 木暮 至 |
| 第2章 革新における企業家と金融(機関)の役割−シュムペーターの「経済発展の理論」を中心にして− | 北條 勇作 |
| 第3章 企業家行動の源泉を探る−新潟県加茂の小企業経営者を事例として− | 今井 雅和 |
| 第4章 本業を軸に新事業転換への一方策−食料品加工機械工業を例とした異業種分野技術との融合を中心として− | 三浦 達司 |
| 第5章 戦略的経営と社内ベンチャー−社内における企業家精神の昂揚を目指して− | 関根 雅則 |
| 第6章 環境保全型社会の構想と起業家精神−ソーシャル・インベストメントとエコファンドの比較分析を通して− | 水口 剛 |
| 第7章 地域金融にみる情報生産−ベンチャー・ビジネスを視野に− | 木元 正司 |
| 第8章 わが国における新規公開市場の現状と課題 | 阿部 圭司 |
| 第9章 群馬県内における高等教育機関の研究活動と産学連携 | 樹下 芳久 |
| 第10章 地域産業政策とビジネス・インキュベーションの時代−地域社会との連携を探る− | 上山 英人・山口 章 |
| 車王国群馬の公共交通とまちづくり |  2001年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 序章 自動車社会の問題点と公共交通の必要性 | 戸所 隆 |
| 第1章 公共交通を軸とした21世紀の都市デザイン | 佐藤 忍 |
| 第2章 公共交通の変遷と地域構造との関係 | 津川 康雄 |
| 第3章 群馬県における乗合バス縮小期にみる諸問題の考察 | 大島 登志彦 |
| 第4章 中心市街地活性化と交通・交流条件の整備 | 長谷川 秀男 |
| 第5章 富岡市における新しい交通まちづくり構想 | 横島 庄治 |
| 第6章 高崎市民の意識と公共交通 | 大宮 登 |
| 第7章 財政からみた公共交通 | 加藤 一郎 |
| 第8章 路面電車の再評価とまちづくり | 西野 寿章 |
| 第9章 公共交通体系の再構築と新しい都市圏の構築 | 戸所 隆 |
| 「現代アジア」のダイナミズムと日本 |  2000年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1部 「現代アジア」の社会文化と日本 | |
| 第1章 文明としての「現代アジア」と日本 | 武井 昭 |
| 第2章 「現代アジア」における宗教と社会 — 「社会の結節点としての宗教」とシンクレティズム | 高橋 正己 |
| 第3章 「現代アジア」の実学思想と日本−「東アジア実学学会」を通して− | 山﨑 益吉 |
| 第4章 中国からみた日本、アジア−外交関係を中心に− | 岡崎 邦彦 |
| 第2部 「現代アジア」の経済社会開発と日本 | |
| 第5章 開発論から見た「現代アジア」と日本 −開発主義論争と日本的アプローチ− | 矢野 修一 |
| 第6章 制度論から見た「現代アジア」と日本 | 竹下 公視 |
| 第7章 東南アジアから見た経済開発と社会開発 | 長谷川 啓之 |
| 第8章 南アジアから見た経済開発と社会開発 −ネパールを事例として− | 辻井 清吾 |
| 第3部 「現代アジア」の産業経済と日本 | |
| 第9章 アジアにおける経済変動と金融 | 吉野 文雄 |
| 第10章 「現代アジア」商業発展の構造と問題点 | 武井 昭 |
| 第11章 「現代アジア」における労働安全衛生 | 池上 徹・岸田 孝弥 |
| 第12章 中小企業とアジア型コーポレート ・ ガバナンス −日本を基点として − | 木元 正司 |
| 近代群馬の蚕糸業−産業と生活からの照射− |  1999年2月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1部 蚕糸業の展開 | |
| 第1章 富国策と蚕糸業−堯舜孔子の道・西洋器機の術− | 山﨑 益吉 |
| 第2章 富岡製糸と近代産業の育成−お雇い外国人を中心に− | 長谷川 秀男 |
| 第3章 初期議会における「蚕種検査法案」反対運動の軌跡−群馬県・島村蚕業者の活動を中心にして | 富澤 一弘 |
| 第4章 組合製糸・群馬社 | 久保 千一 |
| 第2部 蚕糸業の民俗 | |
| 第5章 養蚕・蚕種業の民俗と伝承−群馬県境町島村の見聞や記録から | 千葉 貢 |
| 第6章 群馬の養蚕語彙 | 新井 小枝子 |
| 第7章 絹産業をめぐる諸信仰 | 磯貝 みほ子 |
| 新経営・経済時代への多元的適応 | 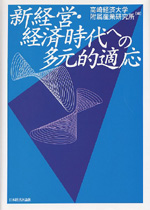 1998年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1部 | |
| 第1章 ドラッカー経営論の斬新性とその限界 | 吉原 茂 |
| 第2章 経済と経営のシステム的関係−ドラッカー社会生態学との関連において | 武井 昭 |
| 第3章 アジア経済の構造変動と政府の役割 | 長谷川 啓之 |
| 第4章 日本経済の構造変革と「憲法改正」への提言 | 安原 和雄 |
| 第5章 企業文化と企業の社会的責任 | 安藤 光俊 |
| 第6章 環境論理の時代の環境監査 | 山浦 映子 |
| 第2部 | |
| 第7章 グローバル化・成熟時代の経営・経済の実態 | 武井 昭 |
| 第8章 高年齢者のための職場改善と参加型人間工学 | 岸田 孝弥 |
| 第9章 情報化時代の新しいワークオプション・テレワーク | 山本 喜則 |
| 第10章 地域中小企業の経営情報化支援 | 山口 憲二 |
| 第11章 証券業界におけるシステム化の歩みと今後 | 野崎 明 |
| 第12章 ビックバン期のメインバンクと中小企業−地域金融のゆくえ− | 木元 正司 |
| 地方の時代の都市山間再生の方途 | 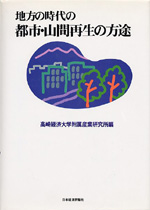 1997年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 1部 | |
| 1章 都市の歴史的展開 | 高階 勇輔 |
| 2章 地域社会の近代化−村落共同体と都市化の研究視角から− | 小池 善吉 |
| 3章 都市分布構造と都市政策のあり方 | 戸所 隆 |
| 4章 都市の特徴と都市制度改革−脱「大衆化時代」の中規模都市の可能性− | 加藤 一郎 |
| 5章 「都市」発展の構造と都市型産業 | 武井 昭 |
| 6章 都市の社会と文化 | 山﨑 益吉 |
| 7章 地域政策の転換と基本課題 | 長谷川 秀男 |
| 2部 | |
| 1章 絹業の展開と地域構造 | 小池 重喜 |
| 2章 利根川筋の「地域用水」−堰と高崎市の事例− | 新井 信男 |
| 3章 二毛作地域における大区画水田営農確立の条件 | 田中 修 |
| 4章 森林・林業の現状と山村振興への視点−林野利用の変換をふまえて− | 西野 寿章 |
| 開発の断面−地域・産業・環境− |  1996年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 町村営電気事業の地域的展開−戦前の岐阜県を事例として− | 西野 寿章 |
| 第2章 艦艇建造と技術導入・開発−1930年代日本の船体溶接技術− | 小池 善吉 |
| 第3章 フランスの「シミュラークル」開発−ユーロディズニーランドをめぐる視座− | 長谷川 秀男 |
| 第4章 汎欧州としての高度情報通信網構想 | 井上 照幸 |
| 第5章 中国雲南省と周辺諸国との相互関係 | 真保 潤一郎 |
| 第6章 「ナショナル・トラスト」の現代的意義 | 山﨑 益吉 |
| 第7章 ニュージーランドにおける農業地域の形成と再編 | 菊地 俊夫 |
| 第8章 地域開発と自然環境−北部ラオスおよび東北タイの開発プロジェクト− | 島崎 美代子 |
| 第9章 インドシナ総合開発フォーラム−その背景と意味− | 矢野 修一 |
| 第10章 環境問題を包摂した地域開発 | 北條 勇作 |
| 群馬にみる人・自然・思想 | 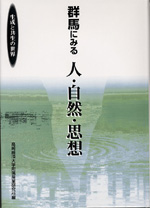 1995年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 1 人と思想−自然・育成・作為− | 山﨑 益吉 |
| 2 「老農」の行方−船津傳次平の思想と足跡− | 飯岡 秀夫 |
| 3 群馬医学界の父・斎藤寿雄−博愛精神を貫いた生涯− | 久保 千一 |
| 4 萩原朔太郎「日本への回帰」−その思想を貫くもの− | 千葉 貢 |
| 5 群馬地域文化の先覚者−井上房一郎九五年の歩み− | 熊倉 浩靖 |
| 6 永杉喜輔と煙仲間 | 野口 周一 |
| 7 地域自立の実践的視角−自然と人間の共生を求めて− | 松下 定光 |
| 8 自然との共生−星野富弘の世界− | 山﨑 益吉 |
| 9 絹産業と民間信仰 | 磯貝 みほ子 |
| 「首都圏問題」の位相と北関東 | 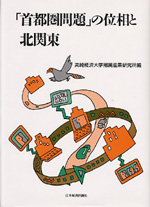 1994年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1部 世紀末の首都圏・北関東の位相 | |
| 1 世紀末世界の構造と日本−産業文明論からの省察− | 高瀬 浄 |
| 2 文化としての「東京」と「首都圏」発展り構造 | 武井 昭 |
| 3 加速化する映像情報化と地域戦略 | 中尾 久 |
| 4 地域情報化と情報政策 | 石川 弘道 |
| 5 産業の構造変動と地域産業政策 | 長谷川 秀男 |
| 6 頭脳立地型地域開発戦略と北関 | 柏木 孝之 |
| 第II部 胎動下の首都圏・北関東の諸相 | |
| 7 「首都圏問題」と北関東諸都市の将来ビジョン−アンケート調査を中心として− | 武井 昭 |
| 8 高速交通時代と物流拠点都市・群馬 | 小林 定義 |
| 9 首都圏における外国人労働者問題−労働安全衛生と技術移転の視点から− | 岸田 孝弥 |
| 10 中小企業政策理念と地方の対応 | 木元 庄司 |
| 11 ニュービジネスと北関東−首都100キロ圏におけるビジネス感覚と都市感覚− | 田辺 忠史 |
| 12 女子短大生の社会環境と雇用問題−群馬県を中心として− | 安藤 光俊 |
| 変革の企業経営−人間視点からの戦略− |  1993年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 21世紀を拓く企業経営の課題と展望 | 木暮 至 |
| 第2章 地方企業の類型とその環境適応行動 | 木暮 至 |
| 第3章 情報と情報技術の活用 | 石川 弘道 |
| 第4章 21世紀への人事革新 | 塩田 咲子 |
| 第5章 管理会計情報の有用性−1980年代以後の動向をふまえて− | 長谷川 恵一 |
| 第6章 創造型流通システムのためのマーケティング | 佐々木 茂 |
| 第7章 企業のスポーツを媒体とした経営戦略の展開 | 高橋 伸次 |
| 第8章 異業種交流への戦略的視点 | 木元 正司 |
| 第9章 企業法務と会社法務部の課題 | 伊藤 壽英 |
| 第10章 過疎地域における「むらおこし」の展開とその課題 | 西野 寿章 |
| 群馬・地域文化の諸相−その濫觴と興隆− | 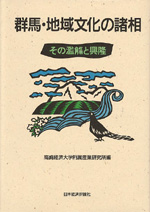 1992年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| I部 地域文化の原点−哲学・産業・行政− | |
| 1 地域文化興隆の哲学 | 山﨑 益吉 |
| 2 生活文化とローカルテクノロジー | 長谷川 秀男 |
| 3 地域文化育成の基礎条件−東京一極集中と群馬− | 竹内 一郎 |
| II部 地域文化の原像−東国・上野・群馬− | |
| 4 東国小宇宙論序説−群馬における地域学構築の前提として− | 熊倉 浩靖 |
| 5 中世唱導と上野国−曽我伝承とその周辺− | 磯貝 みほ子 |
| 6 群馬・「地域文化」の原像 | 飯岡 秀夫 |
| III 部地域文化の展開−人と運動− | |
| 7 群馬の廃娼運動 | 久保 千一 |
| 8 不撓不屈の人・田山花袋−その思想と半生− | 千葉 貢 |
| 9 永杉喜輔論−その人と思想− | 野口 周一 |
| 利根川上流地域の開発と産業 −その変遷と課題− |  1991年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第一章 利根川水系の自然 | 舟橋 説往 |
| 第二章 利根川治水略史 | 風間 輝雄 |
| 第三章 利根川上流域の電力開発史 | 小池 重喜 |
| 第四章 利根川上流域におけるダムの立地展開と水源地 | 西野 寿章 |
| 第五章 地域的水資源の有効利用と水利慣行 | 新井 信男 |
| 第六章 畑地かんがいと群馬県の農業 | 田中 修 |
| 第七章 農村社会変動の課題と展望 | 小池 善吉 |
| 第八章 こんにゃく産業の変革と競争 | 長谷川 秀男 |
| 第九章 林業の活性化と新林業政策体系 | 武井 昭 |
| 第十章 自然・産業・生活環境を考える | 加藤 一郎 |
| 群馬からみた都市型産業と中小企業のニューパラダイム |  1990年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 都市イメージの構造と変容−現代都市に生きる− | 高瀬 浄 |
| 第2章 都市産業と地域産業政策 | 長谷川 秀男 |
| 第3章 都市型産業と中小企業のニューパラダイム | 武井 昭 |
| 第4章 大都市化と中小企業の変容 | 柏木 孝之 |
| 第5章 群馬県における都市再開発の動き | 忰田 昭太郎 |
| 第6章 変貌する群馬県内企業の新規事業戦略 | 小野 吉英 |
| 第7章 流通業と情報ネットワーク | 石川 弘道 |
| 第8章 リゾート時代をむかえる群馬県の民宿・ペンション | 岡田 勉 |
| 第9章 特殊販売契約のトラブルと商品購買行動−高崎市の実態調査を中心に− | 中村 忠 |
| 第10章 自動販売機から都市化を考える | 岸田 弥孝 |
| 第11章 高崎市における地域冷暖房事業の可能性 | 塚越 透 |
| 近代群馬の思想群像II |  1989年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 近代製糸業を支えた工女たち | 山﨑 益吉 |
| 第2章 新島襄における宗教と国家−近代日本知識人のエートスとリベラリズム− | 鈴木 秀一 |
| 第3章 湯浅治郎−プロテスタント「平の信徒」の足跡− | 飯岡 秀夫 |
| 第4章 住谷天来−非戦の思想家− | 久保 千一 |
| 第5章 西田博太郎−桐生高工傑物校長の技術・産業思想− | 熊倉 浩靖 |
| 近代群馬の思想群像 |  1988年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | ブレーン出版 |
| 目次 | |
| 第1章 近代群馬の思想群像 | 山﨑 益吉 |
| 第2章 和田英と「富岡日記」 | 山﨑 益吉 |
| 第3章 萩原りょう太郎と群馬の近代化 | 飯岡 秀夫 |
| 第4章 内村鑑三の思想形成と上州 | 飯岡 秀夫 |
| 第5章 柏木義円の教育観・国家観 | 久保 千一 |
| 第6章 井上保三郎−地域における産業資本家の成立− | 熊倉 浩靖 |
| 第7章 吉野藤一郎−高崎商人の軌跡− | 高階 勇輔 |
| 高度成長時代と群馬 |  1987年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章 高度成長の史的素描 | 高瀬 浄 |
| 第2章 地域社会の変貌 | 山﨑 益吉 |
| 第3章 交通体系の整備 | 松本 新樹 |
| 第4章 基本農政と農業の近代化 | 山﨑 益吉 |
| 第5章 工業の推移 | 北條 勇作 |
| 第6章 商業活動の変化 | 木暮 至 |
| 第7章 観光の変貌 | 北條 勇作 |
| 第8章 地方財政−高度成長はいつどのように始まったか− | 加藤 一郎 |
| 第9章 都市と農村の変貌 | 飯岡 秀夫 |
| 第10章 自然的・歴史的環境の変化 | 山﨑 益吉 |
| 第11章 環境汚染 | 石井 史 |
| 第12章 県民意識 | 上岡 国夫 |
| 高崎の産業と経済の歴史II |  1987年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 高崎経済大学附属産業研究所 |
| 目次 | |
| 第1章 高崎周辺農村と入会問題 | 北島 万次 |
| 第2章 高崎商人のエートス−近江商人を例として− | 山﨑 益吉 |
| 第3章 高崎と群馬の電力産業の史的展開 | 小池 重喜 |
| 第4章 昭和初期の財政と暮らし | 加藤 一郎 |
| 第5章 高崎における戦時統制経済下の商業 | 高階 勇輔 |
| 群馬からみた先端技術と産業構造の変容 日本商工総合研究所 中小企業研究奨励賞受賞
|  1987年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 日本経済評論社 |
| 目次 | |
| 第1章第三次産業革命と産業社会の構図 | 高瀬 浄 |
| 第2章情報化社会と「サービス経済化」 | 武井 昭 |
| 第3章先端技術産業の立地的特質と地域中小企業 | 笹生 仁・柏木 孝之 |
| 第4章技術革新の進展と地域中小企業 | 長谷川 秀男 |
| 第5章中小企業の先端技術の導入と作業変化 | 岸田 孝弥 |
| 第6章群馬県におけるME化と雇用問題の特徴 | 塩田 咲子 |
| 第7章産業の情報化と情報の産業化 | 石川 弘道 |
| 第8章群馬県情報処理産業の現状 | 笠木 通靖 |
| 第9章インテリジェント・ビルと地場建設業の課題 | 塚越 透 |
| 北関東−都市の生活と経済 |  1984年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 高崎経済大学附属産業研究所 |
| 目次 | |
| 第I章 北関東横断道路(仮称)沿いに位置する主要都市圏 | 加藤 敬弘 |
| 第II章 「首都圏」第三層群馬・栃木・茨城の生活・福祉の現状とその特徴について | 武井 昭 |
| 第III章 両毛・水戸線沿線上の主都市の生活・福祉にみる「首都圏」と「定住圏」のあいだ | 武井 昭 |
| 第IV章 北関東の観光の発展における群馬の役割について−筆者の観光新機軸を中心に− | 北條 勇作 |
| 第V章 大規模農家成立の背景(主に北関東)−耗地拡張について− | 新井 信男 |
| 第VI章 北関東諸都市の都市類型と財政状況−高崎市を中心に− | 加藤 一郎 |
| 高崎の産業と経済の歴史 |  1979年3月発行 |
| 高崎経済大学附属産業研究所編 | 高崎経済大学附属産業研究所 |
| 目次 | |
| 高崎藩の成立と城下町 | 北島 万次 |
| 宿駅と交通 | 北島 万次 |
| 伝馬騒動と上州絹一揆 | 北島 万次 |
| 高崎五万石騒動 | 山﨑 益吉 |
| 地租改正と農村の変貌 | 山﨑 益吉 |
| 群馬県の成立と高崎 | 石原 征明 |
| 金融(銀行)の動向 | 石原 征明 |
| 交通(鉄道)の発達 | 石原 征明 |
| 製糸業の史的展開 | 小池 重喜 |
| 商業と工業の発達 | 高階 勇輔 |
| かんがい社会の展開 | 新井 信夫 |
Copyright © 1997-2013
by Institute for Research of Regional Economy, Takasaki City University of Economics
All rights reserved.