アジア通貨危機におけるシンガポールへの影響と対応 7/6
110-065 浦上竜太郎
1 現在のシンガポール経済
国・地域名 シンガポール共和国 The Republic of Singapore
面積 710.3平方キロメートル(東京23区[621.5平方キロ]をやや上回る規模)
人口 518万3,700人(2011年6月末、(人口には、国民、永住者、および長期滞在(1年超)の外国人が含まれる))
言語 国語はマレー語
宗教 仏教、イスラム教、ヒンズー教、道教、キリスト教ほか
民族構成 中国系(74.1%)、マレー系(13.4%)、インド系(9.2%)、その他(3.3%)
※2011年6月末時点。国民・永住者の人口(378万9,300人)の内訳。
公用語 英語、中国語(北京語)、マレー語、タミル語
製造業の現場においては、外資のシェアが70%、国内企業が30%となっている。このように、規制はあるものの、外資の受け入れに積極的である。
また、日本人在留数が約2万4千人である。これは、ASEANで一番ともあり、日本との繋がりも深い。
(現に、自分が滞在していた時、日本人向けスーパーや高島屋や一風堂があり、日本とほとんど変わらない感じがした。)
※現在、シンガポールではシンガポール国立大学を頂点とした学歴社会化と急な少子高齢化が起こっている。自分自身、シンガポールに渡航するまでこれを知らなかった。
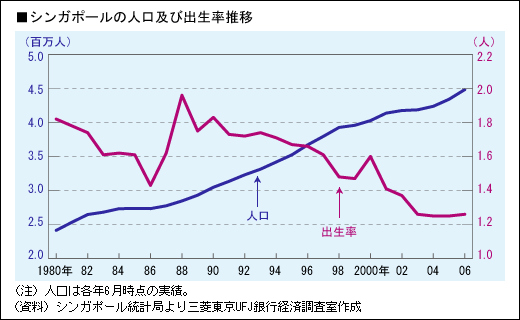
2 アジア通貨危機の影響
タイのバーツ暴落の余波が、マレーシア、フィリピン、インドネシアに広がり、シンガポールドル(以下「Sドル」)にも余波が来た。しかし、当時のシンガポールの経済発展の強さにより経済指標は良く、投資家の信頼を失うことにはならず、他のアセアン諸国に比べて、初期の被害は極小にとどまった。
しかし、通貨危機が長期化するにつれて、シンガポール政府の対応に変化が出始めた。
7月〜8月
1997年2月には、1米ドル=1.4Sドルであったが、7月には1.5Sドルに突入した。そこで政府はシンガポール経済への影響が出る前に、金融システムのあり方に焦点を当て始めた。これには、国際金融センターとしての位置を確立する目的もあった。8月22日には政府はWTO(世界貿易機関)との合致内容に従い、Sドルの国際化を含む金融自由化を検討する「政府特別委員会」を収集した。
10月
10月に入り、対米ドルのSドルの切り下げが加速した。10月7日、フー蔵相が「Sドルが米ドルに対して切り下がったが、他のバスケット(変動為替)通貨(バーツなど)に対して逆に強くなっているため、全体でみればSドルは安定している。」とコメントした。これにより、投資家たちは「政府の介入がない。」と判断し、一気にSドルを売りに出た。その結果、1.5655Sドルまで下落した。
その後、タイの政権不安、マレーシアの98年度予算案の失敗などの不安材料が出る中、10月21日、シンガポール金融管理局がシンガポールの銀行が抱える不良債権の貸付残高に占める比率が「3%以下」と伝えたことに市場が反応し、一時は1.5715Sドルまで下落した。
しかし、27,28日の両日に、シンガポール金融管理局における大規模なSドルの買い占めが行われ、29日以降のSドルは落ち着いたものになった。
次は、この通貨変化がシンガポールの経済に与えた影響について発表する。
参考:『シンガポール:最小限に抑えた通貨危機の影響』 岩上勝一(日本貿易振興会シンガポールセンター)
http://d-arch.ide.go.jp/idedp/TPC/TPC002800_010.pdf
外資に関する規制 ジェトロ
http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/invest_02/
外資に関する奨励 ジェトロ
http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/invest_03/