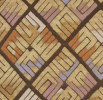着物の柄④
6.古典的な柄
*四季折々の植物、自然(波や雪など)、日用品(扇など)など身近にあるものを素材にして考案された。
*現在…和服はもちろん、和紙や陶器、カーテンなどの模様に幅広く使われている。
☆★代表例★☆
青海波(せいがいは:海の波を図案化し、魚の鱗のように山型に重ねた文様。絞り染めや小紋の着物、帯などによく見られる。)、麻の葉(あさのは:6つの菱形を1枚の麻の葉に見立て、それを放射線状に繋げたもの。麻のように丈夫にすくすく育ってほしいという願いを込めて、産着や子供の晴れ着などに使われる。また、襦袢の文様としても定番化している。)、扇、短冊、鼓、御所車、源氏車(天皇や貴族が使った牛車の車輪を文様にしたもの。半分の形で表したものは片輪車文:かたわぐるまもん
といわれる。)、源氏香(平安貴族の遊びである香合わせに使われた符号で、縦・横の線で表わされる。それを図柄とした文様。)など。
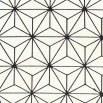
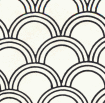 青海波 麻の葉 扇
源氏車 源氏香
青海波 麻の葉 扇
源氏車 源氏香
こんな文様も…
*文字文様…おめでたい文字や願いに通じる文字などを文様化したもの。たとえば、吉、喜、福、寿(壽)、夢、卍(「万」を表す文字。功徳円満を意味し、吉祥の印として用いられていた。)などが例としてあげられる。