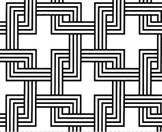着物の柄②
2.吉祥文様
*縁起が良く、不老長寿を願う柄付けである。
*江戸時代…縁起かつぎの意味で、普段着の小袖にも吉祥文様を付けた。
*現代…祝い事の席の着物や帯にふさわしい文様とされている。結婚式などの華やかな席の装いには、これらの文様を複数組み合わせたものが使われることが多い。
☆★代表例★☆
鶴、亀(前回の亀甲文様も含む)、鳳凰、松竹梅、菊、打ち出の小槌・金嚢(きんのう:お金入りの袋)・金函(きんかん:黄金の箱)などの宝物をひとつの布に描いた宝づくし文様など。
鶴 鳳凰 梅



3.役者文様
*江戸時代…歌舞伎役者たちがファッションリーダーだった。
*歌舞伎役者たちが舞台衣装に使い、その後一般に広まった文様。
☆★代表例★☆
六弥太格子(ろくやたこうし:岡部六弥太という役名にちなんでこう呼ばれる)、市松文様(佐野川市松という役者が着用した袴の文様がルーツ)など。
六弥太格子 市松文様