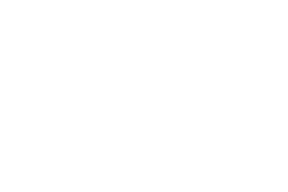平成19年9月3日
ゲームソフトの宣伝
105-370 中川 正隆
1.ゲームソフトの宣伝
ゲームソフトの宣伝活動は、発売の半年前から発売されることが多いです。宣伝活動の内容は主に雑誌への広告やテレビコマーシャルなどを行う宣伝担当、原則的に無料の記事や情報公開を担当するパブリシティ担当、店頭での販促や営業担当などがあります。初期の宣伝活動をティーザーと呼び、大作ソフトを除き多くのゲームソフトは、ゲーム誌への広告や記事掲載が主体です。本来、ティーザー広告はユーザーをじらして期待感を熟成する目的ですが、ゲーム業界では流通業者にアピールする意味も大きいです。
発売の1ヵ月前から宣伝活動は本格化します。専門誌での記事、広告、情報誌やマンガ雑誌への広告展開、店頭でのポスターやプロモーション映像の上映、そして発売が近くなるとテレビコマーシャルと、あらゆる手段でソフトの露出を増やし、ユーザーの注目を集めようとします。宣伝費用が数億円に及ぶゲームソフトから、限りなくゼロに近い予算で担当者が雑誌などの媒体を回るだけのものまであります。一般的に数十万本以上の売り上げが見込まれる大作ソフトはテレビコマーシャルを大規模に行い、専門誌以外への露出も強化します。一方、数万本売ることが目標のものは、ゲーム専門誌を中心とした宣伝活動となっています。また、ハードの普及が見込めるときや、そのゲームソフトがハードメーカーの戦略に合致するとき、ハードメーカー各社からテレビコマーシャルの提供枠などの支援を受けることができます。
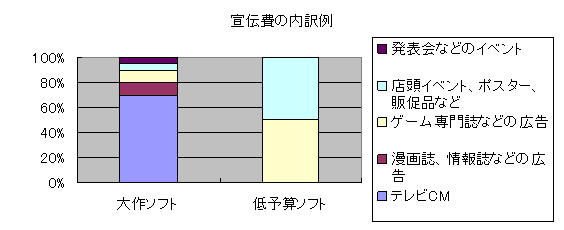
上のグラフが宣伝費の内訳例になります。また、大作ソフトは宣伝費が1億円以上のソフトを指し、低予算ソフトは宣伝費が500万程度のソフトを指します。テレビCMが大作ソフトの宣伝費の内訳の約7割に達していることから、テレビCMのユーザーの注目を集める力が大きいことがわかります。
参考文献
橘寛基(2006)『最新ゲーム業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本』秀和システム